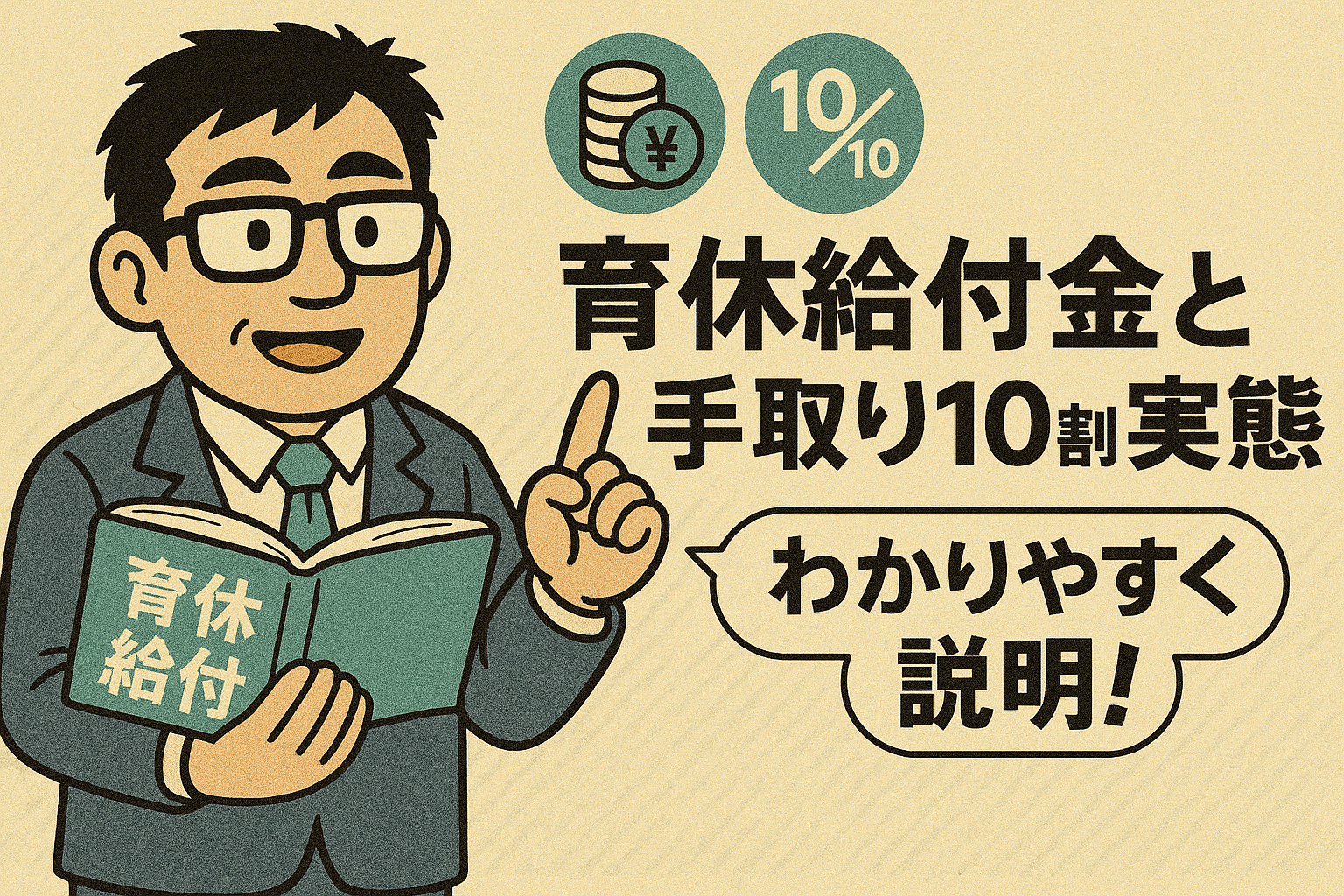💡 この記事でわかること
- 最新の育児休業給付金制度と「出生後休業支援給付金」
- 手取り10割に近づける理由と条件
- 注意すべき落とし穴と具体的な支給額の目安
「夫婦で育休を取りたいけど、収入が減るのが心配…」
「育児休業給付金って、実際どれくらいもらえるの?」
「“手取り10割”って本当に可能なの…?」
共働き世帯にとって、育休は育児と家計の両立をどう実現するかが大きな課題。
でもご安心を。2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」という新制度がスタートします。
これは、従来の育児休業給付金(最大67%)に13%を上乗せし、額面の80%が給付される仕組み。
さらに社会保険料や税金が免除されることで、実質の手取りは“ほぼ満額”に近づくと言われています。
この記事では、新制度の仕組みや支給条件、手取り10割に近づく理由や注意点まで、共働き夫婦にもわかりやすく解説します。
「育休=収入ダウン」と思っていた方こそ、ぜひ最後まで読んで、家族に合った育休プランを考えるヒントにしてみてください。
まずは基本から!育児休業給付金の仕組みとは?
育児休業給付金の支給額と計算方法
✅ 支給額の計算式と例
育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出されます。
▼ 基本の計算式 支給額 = 賃金日額 × 支給率(67%または50%) × 日数
● 賃金日額とは?
- 育休開始前の6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日
- 例)月収30万円 → 30万 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約10,000円/日
● 支給率について
- 育休開始から6ヶ月まで:67%
- 7ヶ月目以降:50%
【具体例】月収30万円・育休を半年取得する場合
賃金日額 = 10,000円 支給率 = 67% 日数 = 30日 × 6ヶ月 = 180日 ▶ 支給額:10,000円 × 67% × 180日 = 約1,206,000円
【7ヶ月目以降も取得した場合(例:トータル8ヶ月)】
7・8ヶ月目(2ヶ月分) 支給率:50% 支給額:10,000円 × 50% × 60日 = 約300,000円 ▶ 合計支給額(8ヶ月間):約1,506,000円
※給付金は2ヶ月ごとにまとめて支給されます。
✅ 支給条件(満たさないと給付対象外)
- 雇用保険に1年以上加入
- 育休中の給与が80%未満
- 月11日以上勤務の月が12ヶ月以上
※いずれかを満たしていないと、給付金の対象外になります。
新制度登場!「出生後休業支援給付金」とは?
新制度『出生後休業支援給付金』とは?
2025年4月から新設される、産後パパ育休(出生時育児休業)専用の給付金制度です。
- 対象:育児休業を14日以上取得したパパで、かつ配偶者も育児休業を取得した場合
- 目的:短期間の休業でも収入の不安を軽減するため
- 支給率:賃金日額の13%(最大28日間分)
この13%は、従来の育児休業給付金(67%)と合わせてトータル80%を実現するための補完給付です。
✅ 出生後休業支援給付金の計算式と例
【基本の計算式】
支給額 = 賃金日額 × 支給対象日数 × 13%
● 賃金日額とは?
→ 育休開始前6ヶ月間の平均月収 ÷ 30(例:月収30万円 → 約10,000円/日)
● 支給対象日数
→ 最大28日間(1ヶ月以内の短期休業向け)
【具体例①】月収30万円の人が28日間取得した場合
賃金日額 = 約10,000円 支給額 = 10,000円 × 28日 × 13% = 約36,400円
---
【具体例②】月収45万円の人が14日間取得した場合
賃金日額 = 約15,000円 支給額 = 15,000円 × 14日 × 13% = 約27,300円
※ ただし、賃金日額が15,690円を超える場合は上限に注意
実質「手取り10割」になる仕組みとは?
実質手取り10割のカラクリ
給付金合計が80%(67%+13%)でも、
社会保険料免除&非課税だから
➡ 実際の手取りはほぼ満額に近い!
よってこのような式になります。
育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)=給付金合計:給与の80%+社会保険料免除&非課税
これらを合わせて『手取り10割』という表現の仕方になっています。
支給が減る原因になるポイント
- 会社からの給与が80%以上 → 給付金支給の対象外になる可能性あり
- 賃金日額の上限超過 → 2025年4月時点での上限は15,690円/日
- 育休中の就業 → 就労日数10日以上 or 80時間以上で不支給になる可能性あり
給付上限がある理由とは?
なぜ上限があるの?その理由を解説
育児休業給付金や出生後休業支援給付金は、**雇用保険制度に基づいて支給される「公的な支援金」**です。
この制度の目的は、子育て中の家庭の生活を支えることですが、すべての人に対して公平な支援を行うため、上限が設けられています。
🔹【理由①】雇用保険制度は「一定の範囲で補償する」設計
雇用保険は、低~中所得者の生活を守る目的で設計されています。
そのため、高所得者でも無制限に支給されるわけではなく、「上限額」を超える部分は自己負担となる仕組みです。
🔹【理由②】制度の持続可能性と財源のバランス
育児休業給付金の財源は、企業と労働者が支払う雇用保険料から成り立っています。
もし高所得者に際限なく支給してしまうと、制度全体の財源が圧迫され、将来的に制度維持が困難になります。
🔹【理由③】「収入補填」ではなく「生活支援」が目的
この制度は、元の収入を100%保障するものではなく、一定期間の生活を支援することが目的です。
そのため、「最低限生活に困らない程度の補助」が制度の基本的な考え方になっています。
🔸補足:実際の上限額(2025年4月時点)
| 給付の種類 | 上限額(日額) |
|---|---|
| 育児休業給付金 | 15,690円 |
| 出生後休業支援給付金 | 賃金日額の13%(上限同様) |
👉 月収換算でいうと、月約47万円(15,690円×30日)程度が上限相当になります。
この水準以上の収入がある方は、給付金の実質支給率が80%未満になるため注意が必要です。
よくある質問Q&A
Q. 出生後休業支援給付金は誰がもらえる?
産後パパ育休を14日以上取得し、配偶者も一定の育休を取得することで支給対象となります。
Q. 給付金の上限はありますか?
2025年4月時点では、賃金日額の上限が15,690円/日です。
Q. 育休中に働いてしまったら?
育休中に10日以上または80時間以上働いた場合、給付金が不支給になる可能性があります。
まとめ:出生後休業支援給付金のキモ
短期育休でもしっかり支給される制度
- 対象は「産後パパ育休」を14日以上取得した人
- 支給額は「賃金日額 × 日数 × 13%」で計算
- 短期間でも3〜5万円程度の支給が見込める
- 高収入の人は上限日額(15,690円)に注意
この新制度により、パパの短期育休も「取りやすく・損しにくく」なります!
最後に:育休を考えているあなたへ
「育休を取ると収入が減るのでは…?」と不安なあなたへ。
2025年からの新制度なら、手取りがほぼ100%に近づく可能性があります。
最新情報をチェックし、パートナーや上司と相談して最適な育休プランを描いてみましょう。
迷ったらハローワークや社労士への相談もおすすめです!